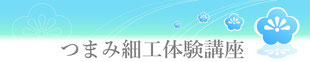佐田つまみ画研究所では、主に花鳥画を主体に作品制作をしています。
自然の風合いを忠実に表現し、不揃いな一枚一枚の花びらの質感、鳥の羽根の様子など、
目を見張る作品が数多くあります。
佐田つまみ画美術館では、短冊サイズから、10号を超える大型の絵画をはじめ、簪(かんざし)、花櫛(はなぐし)、羽子板(はごいた)などのお細工物も揃え、展示しております。「つまみ画」を多くの人に知ってもらうため、初代の残した貴重な作品をはじめ、
現代までの多様な作品を一般公開しておりますので、是非、お立ち寄りください。
~お知らせ~
✨NEW✨
♦2024年11月23日(土)~12月1日(日) 第2回佐田つまみ画研究所つまみ細工展を開催します!✨是非、足をお運びください。
また、開催に際し、出展作品も同時募集いたします!✨今回は、生徒様のつまみ画、佐田つまみ画研究所以外につまみ細工の展示を募集しております。
出展料は5点まで5000円、5点以上10000円となります。11月16日(土)締め切りです。
配送ご希望の方はご相談ください。
「誰かに見てほしいなあ」とタンスに眠るつまみ細工がある方は、是非ご応募をお願いします😊
応募に関する問い合わせは、musashihashiroi@gmail.comまで、お待ちしております!
◆作品の著作権の侵害行為について
◆ご入会希望者様へ★本部教室入会についてよくある質問まとめました
佐田つまみ画教室・美術館見学ご希望の方へ
佐田つまみ画美術館は、原則、第1・2・3週の火・水・土曜日 12:00~16:00の開館となっております。
入館料は、中学生以下300円、大人500円となります。
※祝日を挟む場合は、翌週になります。また、8月は休館月となりますので、ご了承ください。
詳しくは、カレンダーをご覧ください。
美術館、教室運営共に少人数で運営しております、お問合せはメールにて順次お返事させていただきますので
宜しくお願いいたします。
美術館へのご来場・体験講座予約等は事前にメールご連絡お問い合わせいただきますよう
何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



日本の伝統工芸つまみは、四角い布を摘まんで作ることに由来します。
つまみ画は、一枚一枚の布を組み合わせて台紙などに張り付け、花鳥や風景などを表す手芸の事です。
その発祥については、江戸時代に宮中の間で四角い布を畳んで、分箱や琴爪の箱、お守り袋などに
模様を付けることとしてつまみ細工は生まれたと言われております。
江戸後期~になると、つまみ細工も町衆の間に徐々に広がり、櫛(くし)や簪(かんざし)などは若い女性の髪飾りとして
もてはやされました。
明治初期~には応用範囲も広がっていき羽子板、小箱、うちわ、鏡、かんざし、薬玉、祝い飾りや、歌舞伎、文楽などの舞台芸能の
髪飾りなどにも、応用範囲が広がりました。
明治末期~になって、当時のつまみ細工の作者であった吉岡房次郎、船橋水夕、佐田豊山などがつまみの絵画化を試みました。
このようなつまみ細工は明治末期には絵画化が試みられ、つまみ画が誕生しました。

つまみ画の絵画化に尽力したひとりが佐田豊山で、『佐田つまみ画』として現代に至ります。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から